近年、「子どもの体験格差」という言葉を耳にする機会が増えた。経済的な背景や家庭環境によって、子どもが経験できることの幅に差が生まれるというこの問題は、社会全体で取り組むべき課題として認識されているようだが、一歩引いて考えてみると、この「体験格差」という問題提起の裏に、親の「こうあってほしい」というエゴが隠れているのではないか、という問いが浮かび上がる。
「体験格差」は本当に子どものため?
「もっと多様な経験をさせてあげたい」「将来のために今のうちに多くのことを学ばせたい」――一部の親を除き、子供に対してこのように思う気持ちは当然のこととされている。しかし、その「体験」が本当に子ども自身の興味や関心に基づいているのか、それとも親が理想とする「あるべき姿」に近づけるための手段になっているのか、立ち止まって考える必要がある。
例えば、習い事の数を増やしたり、高価な教育プログラムに参加させたりすることが、必ずしも子どもの幸福に直結するとは限らない。子どもが本当に求めているのは、親との時間や、自由に遊べる時間かもしれない。親が良かれと思って与える「体験」が、かえって子どもの自主性や好奇心を奪ってしまう可能性も否定できない。
「理想の大人」へのレールを敷く親のエゴ
多くの親は自分の子どもに、より良い人生を歩んでほしいと願うもの。その願いが、「将来、〇〇になってほしい」「こういう人になってほしい」という具体的な期待となり、その期待を実現するための「体験」を子どもに与えようとする。
もちろん、親が子どもの可能性を信じてサポートすることは重要だが、それはあくまで子どもの意思を尊重した上でなければならない。親が一方的に「これが良い」と決めてレールを敷くことは、子どもの選択の自由を奪い、親の価値観を押し付ける「エゴ」と捉えられても仕方がない。
本当に大切なのは「質の高い体験」より「心の豊かさ」
体験の量や質を競うように子どもに与えるよりも、もっと大切なことがあるのではないか。
それは、どんな環境にいても、子ども自身が「楽しい」「面白い」と感じ、心を豊かにする時間。公園で泥だらけになって遊ぶこと、絵本を読み聞かせてもらうこと、家族で食卓を囲んで語り合うこと。これらもまた、子どもにとってかけがえのない「体験」です。そして、これらの体験は、経済的な格差とはほとんど関係なく、どんな家庭でも与えることができるはずと思いたい。
「体験格差」という言葉が示すのは、子どもが十分な機会に恵まれないことへの懸念ですが、私たちはその根本にある「本当に子どもにとって何が大切なのか」という問いを忘れてはならない。
まとめ:子どもの「今」を尊重する視点
「子どもの体験格差」を考える際、私たちは親自身の価値観や理想を一度手放し、子ども自身の「今」と「心」に目を向ける必要があるのではないか。
子どもが心から楽しんでいれば、それがどんな体験であっても、子どもにとって最高の成長の糧となります。親のエゴではなく、子どもの内なる声に耳を傾けることこそが、真の意味で子どもの未来を豊かにすることにつながると信じ今日も明日も過ごしたいものだ。
そもそも親の子供時代が与えられた内容をこなすだけの人生だったのではないかという考えもよぎるは今日はここでとどめておきたい。





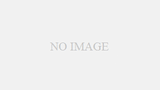
コメント