「子どもが生まれたら、あなたもわかるわよ」。幾度となく、親からこの言葉を浴びせられてきた。まるで、それが親になることの究極の到達点であり、その経験こそが人間性を深める絶対条件であるかのように。そして、私自身もいつしか、漠然とだが「そうなのかもしれない」とうすーく信じていたかもしれない。一種の呪いのように。
やがて時が経ち、私も子どもを産み、育てた。喜びも、苦労も、期待も、不安も、子育てのすべてを体験した。しかし、親が言っていた「わかる」という感覚は、一向に訪れなかったのだ。
期待と現実のズレ
親が語る「わかる」とは、一体何だったのだろう。想像を絶するほどの深い愛情か、それとも自己犠牲の精神か。あるいは、子育ての苦労がすべて報われるような、至福の瞬間を指していたのか。
確かに、子どもへの愛情は計り知れない。初めて抱きしめた時の温もり、小さな手が触れる感触、成長を見守る喜び。出産後すぐにはわからなかったが、ゆっくりと時間をかけてそれらは私の人生を豊かに彩るものだった。だが、それは親から言われた「わかる」という、ある種の絶対的な理解とは異なる感覚だった。
私は、自分の親が感じていたであろう感情を、そのままコピー&ペーストしたようには体験できなかった。私の「わかる」は、私自身の言葉と感情でしか表現できないものだったのだ。
個人の体験は普遍ではない
この経験を通して、私は一つの重要な事実に気づいた。それは、人の体験は、たとえ同じ「子育て」という行為であっても、決して普遍的なものではないということだ。
親が感じたこと、親が「わかる」と表現した感情は、親自身の性格、生育環境、時代背景、そして何よりも、その親と子どもの固有の関係性から生まれたものだ。それは、私の体験とは異なる、親個人の感情であり、決して私がなぞるべき「正解」ではなかったのだ。
私の「わからない」は、私の感性が鈍いわけでも、愛情が足りないわけでもなかった。ただ、私が私なりの「わかる」を体験しているだけなのだ。
「わかる」を押し付けることの危うさ
親からの「わかるわよ」という言葉は、確かに子育ての深淵さを表す一言ではあったかもしれない。しかし、その言葉が持つ、ある種の「押し付け」や「期待」の側面を、私は身をもって体験した。
この言葉は、経験した者だけが知り得る境地があることを示唆する一方で、その境地に達しない者を「未熟」であるかのように扱ってしまう危険性をはらむ。私のように、子どもを産み育てても、親が言う「わかる」を理解できない人間も存在するのだ。
むしろ「わかる」とはなんなのか。自分は子供(大人になっても)の事をよくわかています。と言われているようで何十年たってもフツフツと怒りがこみ上げてくる言葉だ。
「わかる」ことは、人それぞれであり、その形も深さも様々だ。一言で「わかる」とまとめられるほど、人間の感情や体験は単純ではない。たとえ血縁関係にあってもだ。
まとめ:それぞれの「わかる」を肯定する
「子どもが生まれたら、あなたもわかるわよ」。この言葉に、私は理解できなかったという答えを出した。目の前にいる自身の子供と同じ年齢のころ、当時言葉にできなかった感情が思い出される事に気がついた。
幸せな子供時代だったと記憶していたが、パンドラの箱が開いたようだ。
過去を思い出し、怒り虚しさ悲しさがこみあげてくる。
しかし、それは決して自身の子供時代を否定するものではない。
親元を離れて数十年経っても、思考のどこかで支配、もしくは管理されている感覚がある事に気ずく事ができた。この言葉を思い出した事も他の言葉を思い出した事も
子供の誕生は子供の幸せを願う事はもちろんだが、自信の子供時代を良い記憶に塗り替える事ができるチャンスをもらったのだ。
「金食い虫」と言われ育ったがきっと親もそのように言われ育ったのだろう。
悲しい連鎖は私の代で断ち切りたい。そう願い、行動する事をここに誓う。





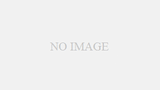
コメント